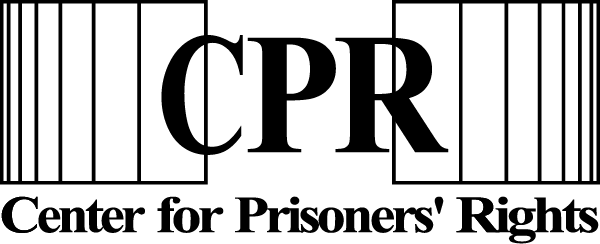岩城法務大臣による死刑執行に抗議する
2015年12月18日
NPO法人監獄人権センター
岩城光英法務大臣は,本日(12月18日)津田寿美年氏(東京拘置所)および若林一行氏(仙台拘置支所)に対し,死刑を執行した。今回の執行は,本年10月に就任した岩城法務大臣による初の執行である。
我々は,本年6月25日の上川法務大臣(当時)による死刑執行に対し,「裁判員裁判による死刑判決の確定が進む中,上訴の取り下げにより裁判員裁判での死刑判決が確定した人々に対する死刑執行は,もはや避けられない。政府は,裁判員制度と世論の支持を根拠に死刑制度維持の責任を市民に押し付けることはやめ,ただちに,義務的上訴制度を早期に導入するとともに、死刑制度全体の見直しを開始すべきである。」と述べた。この言葉を,再度ここに繰り返す。
津田氏は,2011年6月の死刑判決後,弁護人による控訴を自ら取り下げた。津田氏の責任能力に関しては,起訴前に検察庁が簡易鑑定を含めて2度の精神鑑定を行い,起訴後も裁判所による精神鑑定が行われていた。津田氏による控訴取下げは,死刑判決に対する上訴取下げの無効性について基準を示した平成7年6月28日最高裁第二小法廷決定(1)に照らしても疑問の余地があるものであったが,その効力が検証されることはないまま本日の執行に至った。この点において,今回の控訴の取下げは,死刑判決に対する自動上訴制度の導入の必要性を改めて強く認識させるものである。わが国には死刑判決に対する自動上訴制がないため,多くの死刑判決が,上訴審における審理を経ることなく確定してきた。しかし,死刑判決の誤りは,無実の人を死刑とする場合に限られない。責任能力に疑問がある場合や,共犯者間の役割など,死刑か無期かの判断が分かれる要素は様々であり,その判断を誤る可能性は常にある。一昨年以来,3件の裁判員裁判による死刑判決が東京高等裁判所によって破棄され,その判断が最高裁判所によって維持された例は,このことを如実に示している。それゆえに,国連の条約機関は,繰り返し,日本政府に対し,死刑判決に対する義務的上訴制度の導入を勧告してきた 。(2)
また若林氏は,控訴審から否認に転じ犯人性を争っていたが,第一審においては公訴事実を争わず,事件発生から僅か9か月後には判決に至っていた。そのため,被告人の否認主張を踏まえての徹底した事実審理は行われていないまま,死刑が確定している。わが国では,死刑事件においてすら罪責認定と量刑判断のための手続が分離されていないため,同一手続のなかで事実関係を争いつつ減刑を求めることを強いられる事案が生じる。量刑裁量の広い刑法の規定のあり方を含めて,死刑という究極の刑罰を科す手続としては不適切である。
日本政府は,死刑制度をめぐる上記を含めた数々の問題点を直視し,制度の廃止をも視野にいれ,直ちに死刑制度自体の見直しを行うべきである。
監獄人権センターは,今回の死刑執行に強く抗議するとともに,死刑執行の停止,そして死刑制度廃止の政策的実現に向け,今後も取り組んでいく決意である。
以上
(1)「死刑判決に対する上訴取下げは、上訴による不服申立ての道を自ら閉ざして死刑判決を確定させるという重大な法律効果を伴うものであるから、死刑判決の言渡しを受けた被告人が、その判決に不服があるのに、死刑判決宣告の衝撃及び公判審理の重圧に伴う精神的苦痛によって拘禁反応等の精神障害を生じ、その影響下において、その苦痛から逃れることを目的として上訴を取り下げた場合には、その上訴取下げは無効と解するのが相当である。けだし、被告人の上訴取下げが有効であるためには、被告人において上訴取下げの意義を理解し、自己の権利を守る能力を有することが必要であると解すべきところ(最高裁昭和二九年(し)第四一号同年七月三〇日第二小法廷決定・刑集八巻七号一二三一頁参照)、右のような状況の下で上訴を取り下げた場合、被告人は、自己の権利を守る能力を著しく制限されていたものというべきだからである。」
(2)国際人権(自由権)規約委員会(2008年第5回審査総括所見パラ17),拷問禁止委員会(2007年第1回審査総括所見パラ20,2013年第2回審査総括所見パラ15)。