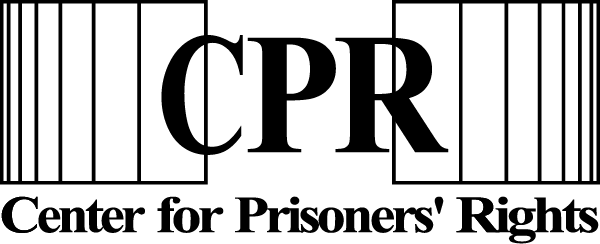名古屋刑務所における度重なる暴行事件と受刑者死亡事件を契機として第二次行刑改革を求める意見書─刑事被拘禁者に対する暴力を根絶するためにはどのような改革が求められているのか─
2023年3月14日
NPO法人監獄人権センター
第1 意見の趣旨
1 全国的な暴力事案・不審死亡事案について徹底した調査を行い、その原因の解明を求める。
2 刑事施設視察委員会の機能と権限を強化し、被収容者のカルテに対しての閲覧の権限を認め、その勧告について、施設当局は尊重する義務があることを定める。
3 全ての刑事被拘禁者が一般市民と同等のレベルの医療を実際に受けられることを確保するために、刑事施設における医療を厚労省所管の通常の医療機関に移管することを求める。
4 医療システムがない警察留置施設の使用はあくまで一時的なものであり、医療不在の留置施設の使用は逮捕後72時間以内に限定し、代用監獄制度は廃止すること。
5 社会復帰のための処遇を担当する職員と保安業務を担当する職員を明確に分離すべきである。
第2 意見の理由
1 人権侵害の連鎖
昨年12月名古屋刑務所における多数の刑務官による特定の受刑者に対する繰り返し暴力が加えられていたという事件が発覚した。刑務官22人が複数の受刑者に対して繰り返し暴行を加える等の行為が行われていたという。
その後、「名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会」が立ち上げられ、刑事拘禁制度の改革のための議論が始まっている。本年2月24日の委員会では、刑務官たちは、「悪ふざけ」や「優越感を味わうため」だったと動機を供述していると、法務省は報告している。また、受刑者三人のうち、二人が職員の言動について、矯正管区などに「不服申し立て」をしようとしたものの、職員が適切な受け付けをせず、断念していた疑いも判明している。不服申し立ての制度が機能していない深刻な状況が明らかになってきている。
一連の暴行が続いていた2022年3月1日に、同じ名古屋刑務所で保護室に収容されていた受刑者が、心筋梗塞と多臓器不全で死亡するという事件が発生した。この事件は、記者発表すらされず、監獄人権センターへの遺族による通報で初めて判明した。監獄人権センターは、本年1月12日に遺族とともに真相解明を求める記者会見を行ったが、その後、病状照会と証拠保全によって次の事実が明らかになった。
2022年2月13日には「胸が痛い」と訴えていたにもかかわらず、救急対応をするのではなく、「大声」を発したとして、繰り返し保護室と静穏室に収容している。同年2月17日保護室解除後静穏室で「呼吸が苦しい」「手指蒼白」「苦しいMRIをとってほしい」などと訴えていたが、22日になってはじめて「血液検査」によって「急性心筋梗塞の疑い」で「重症指定」され、この時点で家族への通知がなされ、豊田厚生病院に入院している。その診断では、「ある程度時間の経過した心筋梗塞と思われる」との診断であり、心臓組織の一部が壊死していた。受刑者は「心臓カテーテル」術にいったん同意したが、医師の説明後に、「もうやめる」として、刑務所に帰り、その後、刑務所では経過を観察していただけで、翌月の3月1日に死亡するに至った。また、刑務所から病院への申し送り文書でも、大声をあげる危険性があるので無理に入院させなくてもよいとの添え書きがなされており、病院側では、手術しないように誘導する説明がされた可能性もある。
本件の根本問題は、心筋梗塞を発症し、胸が痛いと訴えている受刑者を、緊急医療の対象として対応するのではなく、大声をあげている規律かく乱者としてしか見ず、保護室収容などの保安的対応の対象としてしか見なかった点である。そのため心筋梗塞後の緊急期に何の医療も受けることができなかったのであり、このことが受刑者の死亡の結果を招いたと考えられる。まさに、保安と医療とが明確に分離され、医療の必要性を医療スタッフが判断できる仕組みが確立していれば、防ぐことができたと思われる。
ここでは詳しく触れないが、警察の留置施設においても、不自然な死亡例が続いており、 これらの事案は、刑事司法の現場が現在もなお、暴力に支配されていることを示している。このような事態を踏まえ、当センターは、昨年12月20日に
・全国的な暴力事案の調査・解明
・医療へのアクセスの確保/医療システムがない代用監獄制度の廃止
・視察委員会の権限の強化
・国内人権機関の設置
を求める緊急声明を発した。今回の意見書は、このような事態を招いた根本要因を明らかにし、目指すべき改革の方向性を明らかにするものである。
2 社会復帰のための処遇を担当する職員と保安業務を担当する職員を明確に分離すべきである
日本では、長く「担当行刑」という実務運用がなされてきた。これは日常的に親しく収容者と接している第一線の保安職員が処遇の中心を担っている運用である。現場で保安業務に当たる刑務官が、受刑者の社会復帰のための処遇でも中心的な役割を担い、「担当さん」「先生」とよばれてきた。この運用は法的な裏付けはないが、すべての制度が、この運用を前提に組み立てられている。
今回求められる改革としては、刑事施設視察委員会の権限の強化、国内人権機関の創設が当然目指されるべきであるが、より根本的な改革として、人権侵害を未然に予防するために、この担当行刑を見直し、刑務所の秩序維持の機能と社会復帰支援機能と医療提供の機能を明確に分離することが必要であると私たちは考える。
いまも、刑務所の中で、処遇(保安)部門と教育部門とは形式的に分離されているが、組織体制のうえで、教育部門はきわめて脆弱である。監獄人権センターが本年2月にインタビューした元刑務官によると、刑務所の中枢は柔剣道の経験者によって担われ、警備や工場担当が花形とされ、教育については、「本人たちが、例えば教員免許を持っているとか、本人が希望して教育担当になることは多分ないです。正直なところ、教育や分類の仕事は、処遇で使えない人が来ます」とのことである。
ひとりの刑務官に、それも年若い刑務官に刑務所の秩序維持の機能と社会復帰支援機能を、担わせるという「担当制」そのものが、今回の暴力を生み出した根源であって、見直しの対象とされるべきである。
確かに、過去には熟練した刑務官が、秩序維持と社会復帰支援の二つの機能をともに担って成功した例もあったかもしれない。我々の提案に対して、秩序の維持だけに特化した刑務官にどのようなやりがいが見いだせるかという批判があることもわかる。
しかし、私たちが参考にしてきたヨーロッパの行刑の現場では、保安と社会復帰処遇・医療は明確に人的に分離されている。保安担当のモチベーションを下げないで、このような処遇を成功させている例があるのだ。
2017年に日弁連でスペインの刑務所を訪問した。重罪犯を収容する第7刑務所で、所長のエンリケ・バルディビエソ氏から,同刑務所に関する説明を受けたが、同席した副所長のアンドレア氏は,保安体制の担当で,法律の専門家であった。もう一人のホビータ氏は,社会復帰処遇を担当する心理学の専門家でもあり,分類や仮釈放などを担当していた。社会復帰処遇部門のトップは心理学の専門家なのである。このように、刑務所の職員は明確に安全担当と処遇担当に分かれていた。すくなくとも、一人の刑務官が同時に両方の職務を兼務することはない。そして、保安業務だけを担当している職員も誇りあるプロフェッショナルとしてモチベーションが低いようには見えなかった。
日本でも、行刑改革後に美祢や島根あさひ、喜連川などのPFI刑務所がつくられ、野心的なプログラムも実施されてきた。そこでは、外部の民間の会社に社会復帰処遇プログラムの企画まで任せている例がある。島根あさひ社会復帰促進センターのアミティプログラムは、大林組が運営している。
しかし、PFIに収容されているのは、初犯の模範的な受刑者に限られている。今回問題が起きた名古屋刑務所などの累犯刑務所では、担当制のやり方が続いていて、処遇のやり方の根本については、全く手が付けられていない。受刑者の高齢化、刑務官の若年化が進み、実際の処遇の現場で困難が激化していることは、刑務所訪問の時に常に幹部たちから聞く言葉である。
保安担当の刑務官が日常の処遇を通じて受刑者を指導するのが担当制の長所とされてきたが、現在の刑務所では、見回り中に刑務官と受刑者が私語を交わすことすら、籠絡防止のために禁じられている。また、廊下は監視カメラによって監視されており、立ち止まって受刑者と話していただけで、その刑務官は「理由書」をとられ、場合によっては注意処分を受ける。このような環境の下で、社会復帰のための指導の前提となる信頼関係など作りようがない。そういう環境の下で、若い刑務官は、受刑者の人間性を否定し、「嘗められてはならない」「示しをつける」などの意識を生み、継続的な暴力を生み出したのである。
このような運用の実情を改革するには、刑務所の社会復帰処遇を専門職として位置づけ、心理学を学んだ専門家を直接処遇担当に採用し、保安担当とは採用ルートを根本から変えることが考えられる。こうした心理の専門家が、改善更生プログラムを実施するだけではなく、日常的に受刑者に接して全人的な人間的成長を促すことができるよう、職員の多数を占め処遇の中心となる必要がある。仮にそれが難しいとしても、現実に保安業務を担当している高卒採用の多くの職員に対しても、専門的な研修をうけ、試験を受け、資格を得たもののみが、処遇を行うことができる制度とすることが考えられる。このような方策をとることで、職員のモチベーションを下げずに、更生と社会復帰を志向する刑務所へと作り替えていくことができるだろう。
3 自由権規約委員会・国連人権理事会が求める刑務所医療改革=厚労省所管への移管は不可避である
名古屋刑務所における死亡事件の最大の問題点は、医療的ケアが必要な者を保安的措置の対象としたためであると先に述べた。これは、日本の刑務所では、医療の必要性は保安から独立して判断されるべき、という原則が確立しておらず、医療が保安に従属していることから生じた帰結である。医療と保安の分離が無ければ、保安上問題視された受刑者の医療ニーズが見過ごされ、刑務官による虐待があった場合には尚更医療が提供されなくなり、死亡など重大な結果に繋がりやすくなることは自明である。
フランスでは、1994年法により、刑事施設の医療は、一般市民と同様のものとすることが定められ、厚生省所属の医師等によって行われるようになった。行刑職員は医療現場には立ち会わないこととなり、医師の守秘義務も一般の医療と同様のものとなり、医師は、行刑職員に対しても、原則として患者についての診療情報や患者から得た情報を伝えることはなくなった。刑事施設のすべての被収容者に一般の社会保険への自動的な加入が定められた。社会保険料は国が負担し、釈放後も1年間は、特別措置として加入が継続される。被収容者が社会保険に加入することにより、被収容者だけでなく、その家族(扶養すべき配偶者、子など)の分もカバーされるのである。この制度はイギリスでも実現している。
2022年11月3日、自由権規約委員会が日本政府に対して行った勧告(総括所見)では、「家族と連絡する権利および必要な時における医療の提供を含めて、刑事拘禁制度を国連被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)に完全に適合させるために必要な措置を採用するべきである」と勧告された。
マンデラルールは、医療について、「ヘルスケア・サービスは、十分な資格を有し,臨床において完全に独立して行動する人員を擁した多分野にわたるチームにより構成され、かつ,心理学及び精神医学に関する十分な専門知識を含むものとする」(規則25),「臨床上の決定は、責任のあるヘルスケア専門職のみがなし得るものであり、医療分野以外の刑事施設スタッフによってくつがえされ,あるいは無視されてはならない」(規則27)、「ヘルスケア要員は、規律違反に対する制裁その他の制限措置を科すことに関していかなる役割も果たしてはならない」(規則46)とされており、刑務所医療の保安体制からの独立を求めている。
2023年1月31日に「国連人権理事会第4回普遍的定期審査(UPR)」が実施され、115か国から300を超える勧告が示された。普遍的定期的審査(UPR)とは、全ての国連加盟国が各国の人権状況について、世界人権宣言と人権諸条約、国際人権基準等にもとづいて相互に審査を行い、各国が改善すべきと考える点について勧告を発出する制度である。国内人権機関の設立については多くの勧告が出されたが、受刑者を含む刑事被拘禁者の処遇については、代用監獄の廃止、マンデラルールの遵守、拘禁施設の訪問のための拷問防止小委員会と国内防止メカニズムが連携する制度の設立を求める拷問等禁止条約の選択議定書の批准などの問題が取り上げられた。
UPR勧告に対する日本政府の対応は3月末に示される予定であり、これらの勧告について日本政府がどのような対応を示すか注目される。
前述したように、我々が提案している刑務所医療の改革は、フランスに倣ったものだ。フランス行刑の特質を一言で表現するとすれば、「刑務所に市民社会を取り込む」ということである。罪を犯した者に対する処遇を社会全体の課題とし、行刑当局はその営みのうちで、人の自由を拘束し、拘束環境のもとで人間的な生活ができることを保障する。教育は、教育省傘下の教育の専門家(公立学校の教員)に依頼する。図書の整備は、公立図書館の司書が本を選定して蔵書を増やしていく。他の省庁やNPOで、刑務所の中に入ってこようという人がいれば、できるだけパートナーシップを組むようにする。協定を結んで、例えば、離婚した夫婦の一方が刑務所にいる場合に、他方の親の代わりに、子どもを面会に連れてくるNPOがある。こうした活動は行刑当局にはできないことなので、NPOにやってもらっているのである。すべてを刑務所内で自己完結させようとすれば、かならず破綻する。市民社会と共同できることは、原則としてアウト・ソースしていこうとする姿勢に強く感銘を受けた。刑務所医療を厚生省所管とした改革は、実はこのような大改革の一部だったのである。
4 再発防止を超える根本的な改革を実現してほしい
あらたな名古屋刑務所事件について、林真琴前検事総長のロングインタビューが東京新聞に掲載された(2023年1月16日)。
林氏は、名古屋刑務所事件が起きた直後に行刑改革会議が立ち上げられた時に、矯正局総務課長に就任し、行刑改革会議の事務局を務めた方である。その林氏が「再発防止では物足りない」といわれた点は、大変心強いことだ。林氏は、「自分の組織の力だけ高めても達成できない。キーワードは『つなぐ』だ。」「自分の権限や自分の殻に閉じこもるな。検察も刑務所も、そして福祉も、社会もだ。閉じこもっていたら何も解決しない。つながりながら、社会をより良い方向へ変革していってほしい」といわれている。フランスと同じような考えが示されており、同感だ。しかし、刑務所を真に受刑者の社会復帰のための場に変えるためには、個々の刑務官の社会復帰支援の能力を育成するために研修を強化するようなやり方だけでは、限界があるだろう。
今回の第二次行刑改革として、刑事施設視察委員会の権限の強化、国内人権機関の創設が当然目指されるべきだが、さらに、この声明で述べた刑務所の秩序維持の機能と社会復帰支援機能・医療提供の機能を明確に分離することが必要ではないか。行刑の世界を市民社会に開いていくことが、暴力を根絶するための1番目の対策であると考える。
以上