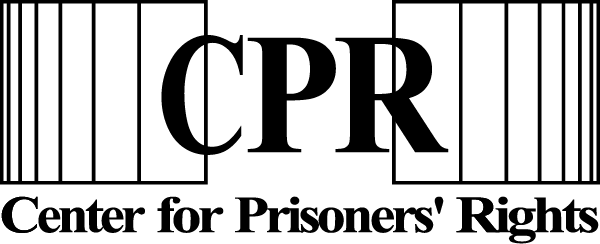刑事司法の現場から被収容者等に対する暴力を根絶し、受刑者の真の更生を目指した処遇の実現を求める声明
2022年12月21日
NPO法人監獄人権センター
本年12月9日、齋藤健法務大臣は臨時記者会見を行い、名古屋刑務所の刑務官22人が複数の受刑者に対して繰り返し暴行を加えていたことを明らかにした。そして同日以降、愛知県岡崎警察署の留置施設で、140時間以上に及ぶ身体拘束の後に被留置者が死亡した事実が報道されるに至った。
これらの事案は、刑事司法の現場が現在もなお、暴力に支配されていることを示している。当センターは、刑事収容施設職員による被収容者等に対する暴力を根絶するとともに、刑に服する受刑者の真の更生を目指した処遇を実現することを強く求める。
これまでに明らかになった一連の事案の経緯は、次の通りである。
12月9日の臨時会見で齋藤法務大臣は、名古屋刑務所の刑務官22人が、昨年11月から本年8月にかけて、複数の受刑者に対して顔や手を叩く、アルコールスプレーを顔に噴射する、尻をサンダルで叩くなどの暴行を繰り返し加えていたことを明らかにした。この問題について法務大臣は、「被害を受けた受刑者に心からおわび申し上げる」と陳謝し、外部有識者による検討会を立ち上げたうえで徹底した調査を進め、関係者への厳正な対処と再発防止策の検討を進める考えを示した。
さらにその後、愛知県岡崎警察署の留置施設で、勾留中の男性(43)が12月4日に死亡していたことが判明した。発表された死因は腎不全であった。男性は延べ140時間以上にわたり、保護室で「戒具」と呼ばれるベルト型の手錠や捕縄で手足を縛られていたほか、幹部を含む複数の署員から暴行を受けていた。男性には統合失調症と糖尿病の持病があったが、署員は糖尿病の薬を飲ませておらず、医師の診断も受けさせていなかったことが、報道で明らかになっている。
名古屋刑務所では、2001年~2002年に複数の受刑者が死傷する事案(いわゆる名古屋刑務所事件)が起きている。この名古屋刑務所事件を契機に、我が国の行刑改革が進められ、刑事被収容者処遇法が成立した。同法の最大の目的は受刑者への暴力を防ぐことにあった。しかし、今回判明した名古屋刑務所での暴行事案は、刑事司法の現場に今もなお暴力を容認する体質が根付いており、20年前の反省が全く活かされていないことを示している。
今回の名古屋刑務所での暴行事案に関与した刑務官は、全員が20~30代であった。実務経験が浅く、暴力で受刑者を威圧する事で施設内の秩序を保とうとしたものと考えられるが、処遇が困難な状況が実際に発生していたのであれば、勤務経験を積んだ熟練の刑務官が現場で処遇にあたり、若手刑務官の実務能力向上の機会とするべきだったと言える。
そして暴力を容認する気風は、警察の留置施設でも根深く残っている。岡崎署で発生した死亡事案は、その一端にすぎない。
かつての行刑改革の際、法務大臣の指示により設置された「行刑改革会議」は、改革の方向性について次のように提言している。
- 「受刑者が、単に刑務所に戻りたくないという思いから罪を犯すことを思いとどまるのではなく、人間としての誇りや自信を取り戻し、自発的、自律的に改善更生及び社会復帰の意欲を持つことが大切である」(行刑改革会議提言10頁)。
- 「これまでの受刑者処遇において、受刑者を管理の対象としてのみとらえ、受刑者の人間性を軽視した処遇がなされてきたことがなかったかを常に省みながら、現在の受刑者処遇の在り方を根底から見直していくことが必要」(同上11頁)である。
- 「行刑施設における刑務官と被収容者との関係は、ともすれば圧倒的な支配服従関係に陥りがちであるから、こうしたことを意識させ、相手の立場に立って考え、対話により相手を説得するなど冷静な対応ができるような能力を修得させる」(同上45頁)必要がある。
今回の一連の問題の背景には、悪人は懲らしめなければならないという牢固な「苦役懲戒主義」が根付いていると見なければならない。我々は、このような考え方を行刑の場から一掃する必要があると考える。今こそ上述の行刑改革会議提言に則り、刑事司法の現場から暴力を排除するための、さらなる改革を推し進めなければならない。それにあたり、当センターは以下の三点の実現を求める。
全国的な暴力事案の調査・解明
名古屋刑務所・岡崎警察署での暴行事案は、この二施設に限定されたものではなく、矯正ならびに警察組織の構造的な問題である。同様の暴行事案が他の刑事施設・留置施設で起きている可能性が充分にある。
当センターには、被収容者等に対する職員からの暴行事案の相談が通年寄せられている。2017年には、新宿警察署に逮捕勾留されたネパール人男性が戒具で拘束され、保護室に収容された後に死亡する事件が発覚し、本年7月には同じく新宿警察署において、ある被留置者が留置官に対し、体調を崩している他の被留置者に毛布を交付するよう求めたところ、ベルト手錠や捕縄で拘束され、保護室に収容され、手首を負傷する事案が起きている。
被収容者・被留置者に対する暴行事案が続出する問題の根源を明らかにするためには、全国の刑事施設・留置施設で発生した近時の暴行事案をすべて調査する必要がある。そして現場で暴行等を止めようとした刑務官・留置担当官等がいたのか、幹部職員にどこまで情報が伝わっていたのか、事件をめぐる全体像を明らかにする必要がある。暴行に関与した刑務官・留置担当官だけの問題として処理してはならない。
医療へのアクセスの確保
保護室への収容や戒具による身体拘束に際しては、独立した医療へのアクセスが確保されていることが欠かせない。とりわけ警察留置施設には、非常勤も含めて医師その他の医療専門職員は配置されておらず、平常はおおむね1カ月に2回、外部の医師が健康診断を行う以外に、被留置者の健康状態を把握する手段がない。今般の岡崎警察署の死亡事案は、こうした医療へのアクセスの欠如が背景にあると考えられる。
加えて、本年12月17日には、大阪府警浪速署に覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで勾留中だった40代の男性容疑者が死亡している。男性は死亡2日前の12月15日朝、「熱がある。息苦しい。病院に行きたい」と申告したが、体温が平熱で呼吸に乱れがないように見えたため、職員は病院に連れて行かなかったという。医療へのアクセスが確保されていれば、その時点で医療上の措置が講じられていたはずであり、浪速署の死亡事案もまた、医療へのアクセスの欠如が要因と考えられる。
警察の留置施設に医療体制が整っていない理由は、留置施設が本来、逮捕から勾留決定までの比較的短い期間に被疑者を留置する施設であるからに他ならない。同様の死亡事案の再発を防ぐため、裁判官による勾留決定後は、速やかに医師らによる医療体制が整っている刑事施設(拘置所)に被疑者を移送し、勾留決定後も刑事施設に代えて留置施設で勾留する「代用監獄」の取り扱いを廃止する必要がある。
視察委員会の権限の強化と国内人権機関の設置
今回の暴行事案でとりわけ重要な点は、名古屋刑務所が名古屋刑務所視察委員会の指摘に対応しなかったということである。
名古屋刑務所視察委員会は本年3月、職員の言動や応対について受刑者の不満が相当数みられると指摘していた。「朝日新聞デジタル」(2022年12月10日)の報道によると、刑務所側は内部調査の結果「収容者への不当な言動や対応などはなかった」と回答したが、視察委は内部調査では限界があると問題視し、第三者による調査など一定の対策を講じるよう所長に求めたという。これに対し、刑務所側は「人権に配慮した応対を行うよう説示していく」と回答したが、今回の暴行事案は、視察委員会の問題指摘後も続いていたことになる。
齋藤法務大臣は本年12月13日の記者会見において、「視察委員会から貴重な意見を頂きながらも、施設運営に適切に反映できていなかったと言わざるを得ない」としたうえで、「名古屋刑務所に限らず、全国の矯正施設におきまして、視察委員会の意見を真摯に受け止め、的確に施設運営に反映させるなど、視察委員会制度の適切な運用を徹底するように、私から指示をしたところです」と述べた。
刑事施設の中には、視察委員会が意見を述べても改善措置を講じない施設も少なくない。視察委員会からの指摘を、単なる「意見」ではなく施設運営に確実に反映させるためには、さらなる法改正を検討し、刑事施設の長には義務として、改善措置を取るよう求めるべきである。
本年11月、国連自由権規約委員会は公表した「総括所見」において、日本政府に対し、最優先課題の一つとして国内人権機関の設置を勧告した。刑事施設や留置施設における暴行事案・死亡事案を防止するためには、政府から独立した国内人権機関を設置し、人権侵害が起きた場合に、同機関による実効的な調査を可能とする体制をすみやかに整備する必要がある。
「悪人は懲らしめるべき」という考えは、誤っている。暴力で罪を犯した人を黙らせても、暴力により抑圧された人の心は更生から遠ざかる。暴力は連鎖する。暴力により心の底からの反省を促すことはできず、暴力の支配する矯正処遇は再犯を誘発する恐れが高まるだけである。受刑者は人として尊重されてこそ、更生への意欲が高まり、よりよい社会復帰、再犯防止に繋がるのである。
刑事司法の現場から暴力を根絶するため、当センターは以上の通りさらなる拘禁制度の改革を実行することを求める。
以上
*PDFをダウンロード