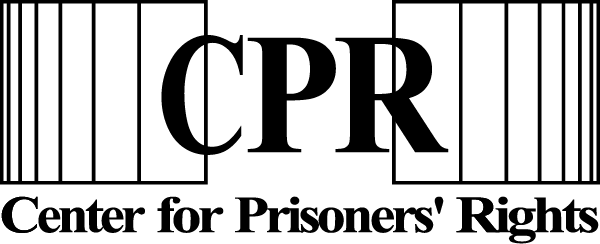ショーシャンクの空に

- 公開
- 1994年、アメリカ
- 原作
- スティーブン・キング
- 監督・脚本
- フランク・ダラボン
- 主演
- ティム・ロビンズ(アンディ)、モーガン・フリーマン(レッド)
監獄映画のナンバーワンを選ぶとすれば、やはりこの作品だろう。 ティム・ロビンズの演技は刑務所生活のつらさ、それと闘う人間の不屈の精神を凝縮している。 この演技のためにティム・ロビンズは実際に刑務所生活を体験し、受刑者からも意見を聞いたという。 アンディを支える老受刑者レッドを演ずるモーガン・フリーマンの演技もアカデミー賞の助演賞を獲得した名演だ。 彼が仮釈放の審査の時に見せる演技が見物だ。人間にとっていかに自由が大切かをこれほど深く考えさせてくれる映画はないだろう。
詳細はこちら告発

- 公開
- 1994年、アメリカ
- 監督
- マーク・ロッコ
- 主演
- クリスチャン・スレーター(ジェームズ)、ケビン・ベーコン(ヘンリー)
アルカトラス刑務所を舞台に刑務所内の虐待をテーマに描いた作品。 意外にもクリスチャン・スレーターの方が弁護士役である。 ホールという名の暗室拘禁が規律秩序の維持の名目で拷問の道具として使われている。 日本でも戦前には認められていた「重屏禁」がこれに相当する。
詳細はこちらザ・ハリケーン

- 公開
- 1999年、アメリカ
- 監督
- ノーマン・ジェイソン
- 主演
- デンゼル・ワシントン(ルービン・ハリケーン・カーター)、 ヴィセラス・レオン・シャノン(レズラ)
無実の罪でとらわれた黒人ボクサー、ルービンが文通で知り合った黒人少年レズラとカナダ人のグループに 助けられながら再審を勝ち取るまでの物語。映画にも使われているボブ・ディランの「ハリケーン」は、 彼の再審のためにディランが作曲した名曲である。刑務所での面会の場面が時代ごとに変わっていく。 ハリケーンと妻との別れの場面には面会室に仕切り番があったのに、 レズラとの面会のときにはテーブルを囲んで飲み物を飲みながら話ができるようになるなど、 時代考証もしっかりしている。
詳細はこちらデッドマン・ウォーキング
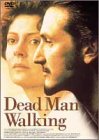
- 公開
- 1995年、アメリカ
- 原作
- ヘレン・プレジャーン
- 制作・監督・脚本
- ティム・ロビンズ
- 主演
- スーザン・サランドン(シスター・ヘレン)、ショーン・ペン(マシュー)
アカデミー主演女優賞受賞、ベルリン映画祭男優賞受賞
ルイジアナ州立刑務所で死刑を待つマシューと面会したシスター・ヘレンが、 事件の真相に疑問を抱き弁護士に再審を依頼する。 日本の死刑廃止運動の招きで来日したこともあるプレジャーンの手記を忠実に映画化した。 監督は「ショーシャンクの空に」で主演したティム・ロビンズ、 主演はティムのパートナーのスーザン・サランドンである。 彼らは実際にも死刑廃止運動や無実の黒人ジャーナリスト、 ムミア・アブジャマールの救援などに取り組んでいる。
詳細はこちらパピヨン

- 公開
- 1973年、フランス=アメリカ
- 原作
- アンリ・シャリエール
- 制作・監督
- フランクリン・J・シャフナー
- 主演
- スティーブン・マックィーン(パピヨン)、ダスティン・ホフマン
監獄映画の金字塔。フランスの流刑島から、脱出を繰り返すパピヨンの不屈の精神には目を見張る。 監獄が人間性を破壊する場所であること、とりわけ独房拘禁の非人間性を余すところなく描き出した。
詳細はこちら終身犯

- 公開
- 1962年、アメリカ
- 監督
- ジョン・フランケンハイマー
- 主演
- バートランカスター(ロバート・ストラウド)、 カール・マルデン(ハーベイ・シューメーカー 所長)、 テルマ・リッター(エリザベス・ストラウド 母)、 ベティ・フィールド(ステラ・ジョンソン)、 ネビル・ブランド(ブル・ランソム 親切な看守)
母親の大統領への嘆願で死刑から終身刑に減刑されたストラウドの 長い受刑生活を丹念に描いた刑務所映画の古典的名作。 荒れ果てていたストラウドが雨の運動場で傷ついた小鳥を助けたことから、 人間性を取り戻していく。そして、ついには鳥の病気の治療のためのベストセラーの著者となる。 バートランカスターは、この演技でアカデミー主演男優賞にノミネートされた。 刑務所拘禁のもつ非人間性をここまで描き切った映画はないだろう。 ストラウドとシューメーカー所長の「矯正」をめぐる確執は、 刑務所に関するどんな哲学書も及ばないほど示唆に富んでいる。
詳細はこちら父の祈りを IN THE NAME OF FATHER
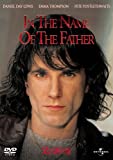
- 公開
- 1993年、アメリカ
- 原作
- ジェリー・コンロン
- 制作・監督・脚本
- ジム・シェリダン
- 主演
- ダニエル・デイ・ルイス(ジェリー)、エマ・トンブソン(弁護士)、ピート・ポスルスウェイト(ジェリーの父)、ベルリン映画祭金熊賞
“ギルフォード・フォー事件”
1974年10月5日、ロンドン郊外の町ギルフォード。IRAのテロが拡大する中で、二軒のパブが爆破される。あまりに衝撃的な“ギルフォード・フォー事件”の幕開けであった。 その後も爆破事件は続き、解決を迫られた政府は急遽「テロ防止法」という新たな厳罰法を制定する。これは警察に、容疑者を弁護士と隔離したまま7日間拘留できるといった大幅な権限を認めるものだった。ジェリー・コンロンの幼なじみであるポールは、この新法によって逮捕された。隔離されて手荒な取調べを受けたポールは、無実であるにも関わらず“自白”をさせられ、共犯者としてジェリーの名を挙げてしまう。そして逮捕されたジェリーも遂に、厳しい尋問に屈して供述書に薯名してしまったのである。そのため彼らのヒッピー仲間のパディやキャロルも事件に巻き込まれ、逮捕されることになる。この4人こそが、マスコミが“ギルフォード・フォー(=ギルフォードの4人)”と呼んだ容疑者である。その後、ジェリーの父ジュゼッペや叔母一家たちも、警察が仕掛けた罠に運悪く掛かってしまいテロの協力者として逮捕されてしまう。そして、彼らを犯人と決定付ける証拠もなく、当初の自白を撤回したにも関わらず、ジェリーとポールは無期懲役、パディやキャロルは30年、ジュゼッペや叔母一家も12年以上の懲役刑を宣告され、刑務所に投獄されたのであった。
父と子の葛藤
刑務所の中でジュゼッペは一縷の望みを託し、再審を訴え続けて市民団体に手紙を書き続けたが、そんな父をシニカルに眺めるだけのジェリーは無為な日々を送っていた。しかし獄中での気の遠くなるような歳月の中で、ジェリーは静かなる闘いに魂を投じる父の姿を正視していくことになるのだった。
そんなある日、IRAの闘士ジョーが刑務所に送られ、例の爆破は自分の犯行で当局は真相を知っていながら隠していると告白する。しかしIRAの力は借りるべきでないと考えるジュゼッペは、無実を証明したいというジョーの協力を断固として拒絶する。その後、元々肺血栓を煩っていたジュゼッペは刑務所内で次第に健康を害していき、遂に獄中で無念の死を遂げることになる。この時から、ジェリーの中で何かが変わったのだった。一見、弱い人間ジュゼッペ。しかし、真面目一本で生きてきた男の意地が感じられる。ジュゼッペ役のピート・ポスルスウェイトの、静かながらその奥底に揺るぎない力強さをもった演技には迫るものがある。絶望の淵にありながら、正義を求め続けるその姿に子供ならずとも心打たれるものがあったと言えるだろう。
父の名において
事件から10年以上が経過し、ジェリーは父の汚名をすすぐため、再審請求運動に身を投じていた。そして女性弁護士ガレス・ピアースのたゆみない調査の結果、ジェリーとポールのアリバイを証明するホームレスの証言が警察によって隠蔽されていたことが発覚する。1989年、この決定的な証拠によりギルフォード・フォーの有罪判決は遂に覆る。事件から実に15年後のことであった。ジェリーはジュゼッペから信念と生きることの尊厳を学んだ。そして、その父のための努力が、ここに実を結んだのである。
定職も持たない遊び人で、素直で大人になりきれない主人公ジェリーをダニエル・デイ・ルイスが好演し、オスカーにノミネートされている。この遊び人ぶりが、後半に本気で権力に立ち向かうジェリーの行動に深みを与えているとも言えるだろう。事件の解決と世間への体面を気にするあまり、その後明らかになった真相をもひた隠して彼らを犯人に仕立てた警察。それを鵜呑みにして彼らを激しく非難するイギリス大衆のアイルランド人差別。そういった人間の醜態が暴露されていくとともに、父と子の確執という永遠不滅のテーマが感動的に綴られていく秀作であると言えるであろう。
アイリッシュ音楽
また、この映画にはシニード・オコナーやU2のボノら、アイルランド人のアーティストが曲を提供していることも特筆しておきたい。特にオープニングの方で流されるボノの“In The Name Of The Father”は、かなり劇的に使われており迫力がある。
映画の原題でもある“In The Name Of The Father”は、生身の人間としての父ジュゼッペだけでなく、父なる神をも連想させるように意図しているという。そこには、暴力の輪が断ち切られることへの願いが込められていると監督のシェリダンは語っている。
フィクションとしての現実性
この映画は、イギリスの刑事司法制度を根底から揺るがした冤罪事件“ギルフォード・フォー事件”を題材とした衝撃の人間ドラマである。『父の祈りを』の脚本は、ジェリー・コンロンの回想録「Proved Innocent(邦訳題「父の祈りを」)」に基づいている。
ただし、映画で描かれていたようなジェリーとジュゼッペが同じ刑務所にいたという事実はなく、実際はお互いに手紙をやり取りしていただけである。映画化する過程で仕方なかったとはいえ、かなりの脚色が入っているのは少し残念と言えよう。
冤罪防止へ向けて
無実を証明して自由を取り戻すために闘う内、父親との強い絆と生きることの真剣さに目覚めてゆく青年ジェリーの心の軌跡を追いながら、英司法制度を根本から揺るがし今も様々なグレー・ゾーンを残すこの事件に真っ向から光を当てており見応えがある。警察刑事証拠法(1984年)による弁護士との面会権の保障、取調べ時の録音の義務付けなどは、この事件の与えた影響も少なからずあるとされている。また、1995年の刑事上訴法の改正による刑事事件再審委員会の設置や、1996年の証拠開示法の制定も、この事件の経過が大きく関わっている。
2005年2月には英首相ブレアがジェリーらに対し、公式に謝罪した。無実の罪を着せられた人に対する態度、そして冤罪を防止しようとする姿勢について、日本と比較しないではいられない。
Lenny The Kid
間違えられた男 The Wrong Man

- 公開
- 1956年 アメリカ
- 原作
- マクスウェル・アンダーソン
- 監督
- アルフレッド・ヒッチコック
- 脚本
- マクスウェル・アンダーソン、アンガス・マクファイル
- 主演
- ヘンリー・フォンダ、ヴェラ・マイルズ
全ては1つの小さな間違いから始まった
心配性だが優しく美しい妻がいて、幼い息子が2人いて、ニューヨークでクラブのコントラバス奏者として生計を立て、ローンは残っているが平和な生活。クリストファー・エマニュエル(マニー)・バレストレロは、「幸せ」と呼べる生活を送っていたはずだった。 しかし、ある日マニーが妻の保険を担保にして金を借りようと保険事務所を訪れた時に、全てが変わってしまう。彼の顔が連続強盗事件の犯人の顔に似ていたことから、そこの女性事務員が彼を強盗犯であると勘違いしたのだ。その1つの間違いから、彼の生活は崩れていく。
容疑者を見る人々の眼差し
事務所の事務員達に通報され、マニーは何が起こったのか分からないまま警察署に連行される。警察署で説明を受け、マニーは連行された理由を知った。しかし、目撃者たちの多くは、「容疑者として」彼を見つめて犯人であると証言する。また、運が悪いことに、犯人が残した脅迫文の文句を警察がマニーに書かせた際、彼は犯人と同じ部分でスペル・ミスをしてしまう。このことからマニーを犯人と断定した警察は、マニーを真犯人として起訴したのだった。この映画の中で注目すべきなのは、取調べをした警察官も、彼を犯人だと言った証人達も、誰一人として悪意を持っていたわけではないということであろう。全員、世の中から犯罪を減らすために、自分の果たすべき義務を果たしているだけなのである。誰も自分の行動で誰かを害そうとは考えていないし、もちろん無実の人間を陥れようとなんて露ほども考えていない。しかし、実際に無実の人間が追い詰められていくという現実があるのだ。
人間の思い込み。どんなに公平に判断しようとしても、「容疑者」であるということだけで、最初から視線が違うのである。犯人でないと知っている観客の眼から見ているから私たちは間違えないが、実際の事件の場合はそうはいかない。思い込みによって悲劇を招かないためにも、捜査や裁判では、厳密な手続きと注意深さが強く要求されているといえよう。
失ったものの大きさ
また、「容疑者として嫌疑をかけられる」ということの影響力の大きさも見落とせない。私たちは普通、被告人の無実が証明された場合、それで冤罪が晴れたわけだから「めでたし、めでたし」と思ってしまいがちである。だが、実際そうなのだろうか。
自由を奪われていたという事実は、冤罪が晴れても変わらない。この映画にもあるようにアメリカには逮捕直後からの保釈制度があるため、保釈金さえあれば保釈してもらえる。しかし日本では、起訴されるまで保釈されることはありえない。最長で23日間の勾留期間、そして冤罪にも関わらず有罪とされ刑に服していた期間は戻ってくることはないのである。
また、周囲に与える影響もあるだろう。この映画の中で、心配性の妻ローズはあまりの心労から精神病になってしまう。そのためローズは専用の療養所に入院し、家族はバラバラに暮らすことになってしまっていた。冤罪が晴れ、マニーは嬉々として入院中のローズに報告に行く。その報告で精神病が治ると信じて。しかし、そんな奇跡は起こらない。映画の中でも、現実でもである。一度崩壊した生活、そして精神は、そんなに簡単に修復できないという苦さを、私たちは直視しなければならないのではないだろうか。
それまで描かれなかったようなサスペンス
この映画は、サスペンス映画の代表者とも言えるアルフレッド・ヒッチコック監督が56年に作ったものである。しかし、冒頭でヒッチコック自身が「私は今まで様々なミステリー映画を発表してきたが、この作品は実際に起こった事件を基にしている点で、まったく毛色が違う。事実は小説よりも奇なり」と述べている通り、異色のサスペンスであると言えよう。
マニーを演じるヘンリー・フォンダの、当惑する時の演技が特に素晴らしい。派手さも激しさもなく、ただ単に当惑する気持ちだけを演じることで、かえって最も自然で説得力のある演技になっていると思われる。この映画には陰謀も、アクションもない。1人の男が、ある日突然嫌疑をかけられたことで全てを失っていく。その過程を、まるでドキュメンタリーを観ているかのような感覚で私たちは眺めるのである。地味ではあるかもしれないが、映画全体に漂う緊張感と言い知れない危機感を見事に描き上げている。あまりにも起こりそうで、かえって描かれなかったような題材であり、警察への警鐘を鳴らしているといえよう。
“疑わしきは被告人の利益に”
刑事訴訟法を勉強すると、“疑わしきは被告人の利益に”という原則が出てくる。これは、真偽が不明な場合には被告人にとって有利なようにされるということである。したがって、犯罪事実の存否が合理的な疑いを入れないまでに立証されない限り、被告人は無罪であると推定されるということになるのである。
05年7月イギリスにおいて、自爆テロ犯と間違われたブラジル人の青年が射殺されるという事件が起こった。テロ対策という名の元に、職務質問も停止命令もなく、無防備な一市民が警察によって背後から撃ち殺されたのである。頭部に7発と肩に1発。これは、殺人そのものではないのか。しかも、当時警察によって発表されていた不審な行動や極端な厚着などについては、その後の調査で否定されている。イギリス政府は謝罪しているものの、今後も対テロ法を変えるつもりはないとし、殺害を意図する発砲も許容するという。
疑惑で人が殺される、そんなことが正当化されるような時代へと暴走していこうとしているのが今なのだ。この世界は、こんなにも危うい。
Lenny The Kid
ジャスティス 闇の迷宮(Imagining Argentina)

- 公開
- 2004年 アメリカ/アルゼンチン/スペイン/イギリス
- 原作
- ローレンス・ソーントン
- 主演
- アントニオ・バンデラス(カルロス)、エマ・トンプソン (セシリア)、クレア・ブルーム(スターンバーグ)
人が消える
1976年に軍事政権が成立したアルゼンチン。その首都ブエノスアイレスでは、市民の失踪や誘拐事件が相次いでいた。
女性記者のセシリア(エマ・トンプソン)は一連の失踪事件が政府の反政府勢力弾圧の一環である証拠を掴み、正義感からそれを記事にして発表する決意を固める。しかしある日、当のセシリアも失踪してしまうのだった。児童劇団の演出を担当し ている夫カルロス(アントニオ・バンデラス)は一人娘のテレサとともにセシリアの行方を捜すが、警察にも相手にされず空しい時が過ぎてゆく。そんなある日、カルロスは自分に不思議な能力があることに気づく。失踪者を身内に持つ人間の体に 触れると、その失踪者が失踪した時の様子やその後の運命が見えるのだった。
哀しい事実が見えるだけ
カルロスは政治とは無関係の人物であったが、特殊な能力を備えていて、失踪した人々の消息が見えてしまう。しかし、見えても何もできず、連れ去られた人々が置かれている悲惨な状況を感じ取り、苦悩するだけである。そして政府の魔の手は、 妻だけでなく彼の愛する娘や同僚にまでも及んでいく。
彼は少ない手がかりを元に、必死に秘密刑務所を探し出そうとする。そこで判明していく現実の酷さに怒り、一度は拉致・誘拐を指導している軍部の高官を暗殺しようと銃を構えた彼だったが、その引き金は引かない。その高官にも愛する家族がい るのである。暴力に対して暴力をもって応えたとしても、何も生み出しはしない。新たな悲しみと憎しみを増やすだけだと気付いた彼は、銃による解決を捨てるのであった。
死に値するような拷問
カルロスが必死に行方を捜す中、目を覆いたくなる程の拷問をセシリアは受けていた。軍の秘密監獄に拉致・監禁されたあげく、軍のメンバーに集団暴行され、更には自分の娘までも同じ扱いをされたあげく惨殺されてしまうのである。
逮捕状もなく、何の前触れもなしに連れ去られて行く学生。暴行されたあげく、下着のまま銃殺される少女たち。誘拐された家族を捜すための教会での集会に銃を持った軍部が突入し、一瞬にして連れ去られた新たな犠牲者たち。秘密刑務所から命 からがら逃げ出そうとするが、失敗して更なる拷問を受ける者。…こんな人権侵害が行われていたということに、驚きとともに戦慄を感じる。
体当たりの演技
カルロスを演じたアントニオ・バンデラスは、本作への出演を切望したという。単なる一市民に過ぎないカルロスが愛する妻や娘を奪われ、なすすべもなく現実を見る。静かに内にこめた怒りを見事に表現している演技である。それは多くのアルゼ ンチン市民の気持ちを代弁するものではないだろうか。彼以外この役は考えられない程、見事な演技であったと言えるだろう。
そして、何といってもエマ・トンプソンの体当たりの汚れ役である。人間の尊厳を問う映画としても避けて通れない辛いシーンが連続した。彼女の役者魂を観る思いがする。彼女自身、非常に過酷な撮影だったと語っていたが、どんな状況下でも 信念を曲げず、生きようとする逞しい女性を演じきっている。
ドラマチックな展開はないが静かに語りかけ、心に刻み込まれるような映画である。この映画に対する2人の思いは、演技からヒシヒシと伝わってくると言えるだろう。
心の闇
通常の刑務所と違って秘密刑務所は、その存在すら隠されている。これこそが秘密刑務所の恐ろしさの根源である。なぜなら、その刑務所に誰が入れられていようが、またその中で拷問されようが死のうが、分からない。人権侵害の証拠を得るこ とが極めて困難であり、世間から完全に閉じられた秘密刑務所は、究極の人権侵害を生み出す可能性が高いのである。拘禁施設の透明性を高めることが持っている決定的な重要性を再確認することができる。
この作品は、ローレンス・ソーントンの原作を基に、クリストファー・ハンプトンが脚色し、自ら監督したものである。独裁政治で腐敗した70年代、アルゼンチンで3万人にも及ぶ国民が秘密警察に拉致され「消された」事実をもとに、人間の尊 厳を問う衝撃的なポリティカル・サスペンスであると言えるだろう。アルゼンチンのブエノスアイレスでは今でも毎日、子供を失った母親達が写真を持って立ち続けているという。軍事政権が崩壊して20年近く、人権侵害の首謀者達は恩赦されて しまい正義は実現されていないのである。行方が知れなくなった家族を、恋人を、友人を待ち続け、正義の回復を求めている人々が残されたのである。この映画は彼らと残された人々に対する鎮魂歌とも言えるだろう。
悲劇を繰り返すな
「悲劇は、いつ繰り返されるとも限らない」というカルロスの言葉が印象深い。真実は闇に葬り去られていくが、それを忘れないで伝えるのが使命なのだと最後の集会で彼は語る。
アルゼンチンの悲劇は終わったかもしれない。
アムネスティはチェチェンとイングーシにおいて、ロシア政府が関係した拷問や誘拐、一般市民に対する秘密裏に行われた拘禁など、終わりの見えない甚大な人権侵害に関する現地調査報告を2005年9月に発表していた。今でも、同じような悲 劇が続いているのだ。
この映画の最後に飾られる言葉は「i nunca mas!」である。アルゼンチン語で、「悲劇を繰り返すな」という意味だという。そう、これ以上、悲劇を繰り返さないためにも、私達は真実を直視しなければならないのではないだろうか。
Lenny The Kid
グリーン・フィンガーズ(Greenfingers)

- 公開
- 2000年イギリス
- 監督・脚本
- ジョエル・ハーシュマン
- 主演
- クライブ・オーウェン
ガーデニングを始めた受刑者たち
コッツウォルズ地方にあるエッジフィールド刑務所。鉄条網も高い塀も監視カメラもない、この開放刑務所に移送されてきたにも関わらず、受刑者のコリン・ブリッグスは生きる希望も失っているような状態だった。部屋に植木鉢を置いて可愛がっている同室のファーガスは、そんな彼に1袋の種を手渡す。冬に種を蒔いて花を咲かせるのは難しいし、最初は下らないと思っていたコリンだったが、試しに蒔いてみることに。そして春、蒔いた種からニオイスミレが花開いた。コリンには園芸の才能があったのだ。
この花を他の受刑者がサッカー・ボールで踏んづけてしまったことから、受刑者同士のちょっとした諍いがあり、それをきっかけに、所長のハッジの粋な計らいでこの刑務所の新たな更生プログラムとしてガーデニングが導入されることとなる。無理だと言うコリンにファーガスが言う。「もう囚人は飽き飽きだ。庭師になろうぜ!」
天才庭師として
更生プログラムの一環として庭造りを命じられたチームを構成するのは、ガーデニングなんてガラではない受刑者たちばかり。しかし見事美しい庭を造ることに成功し、園芸専門家ジョージナの助言もあってかめきめき腕を上げていく。ガーデニングによって命を育てる喜びを初めて知ったコリンは、その才能を認められて「グリーンフィンガーズ(天才庭師)」の異名をとるほどになり、チームは近隣の屋敷の造園を任せられるようになるのであった。さらに、囚人たちによるガーデニングという話題性もあってか、ついに女王陛下も出席するというハンプトンコート・フラワーショウへの出場資格が与えられるのである。
しかし、ここで事件が起こる。造園をしていた近隣の屋敷に泥棒が入り、その手引きをしたのがチームの受刑者の1人であると疑われたのだ。これにより外部通勤の制度はマスコミや世論から攻撃を受け、フラワーショウへの参加も危うくなるのであった。
日常の幸せ
奮闘の結果、最終的にはコリンらはショウに出展することになるのだが、その庭園が素晴らしい。野生の草花が散りばめられた高速道路の土手をイメージしたもので、日常の自然の中にある美しさを引き出していた。それは途中に「作らされた」ロック・ガーデンとは対照的である。刑務所をモチーフにしたロック・ガーデンは人工的で、人間を強制することが更生につながるという印象を与える。それに対して、素朴で着飾らない土手のガーデニングが、なんと自然で美しいことだろう。
人間味
2000年に製作された本作は、驚くべきことに実話がもとになっているという。プロデューサーがニューヨーク・タイムズの1998年7月に掲載されたポーラ・デイツ記者の『英国でベルフラワーを育てる自由』という記事を読み、アイディアを思いついたのだとか。
園芸専門家のジョージナが受刑者たちと打ち解けていく過程、ジョージナの娘プリムローズとの恋、フラワーショウへの憧れ、自分の罪の告白など、人間味溢れるような心の温かくなる映画である。特にコリン役のクライヴ・オーウェンの寡黙な演技が、淡々と進むストーリーに合っている。また、飄々としたファーガス役のデビッド・ケリーや、素直な感性を持つジョージナ役のヘレン・ミレンの演技が、さらにストーリーに花を添えている。
命を奪った者と命を与える者
コリンが仮釈放の審査会で述べる言葉が印象的である。「命を奪うことの意味を知っているのは俺だけだ。誰か俺の命を奪ってくれとも思っていた。…だが、命を与え育てることを知った。…俺は庭師だ。この方法はとてもいい、推薦する。」その言葉の確かさに心打たれる、素晴らしいシーンである。
人との関わりを拒否して殻に閉じこもろうとしていたコリンに、花の種をプレゼントすることで命を育むことの尊さを気付かせたファーガス。過去に他人の命を奪ってしまったことへの自責の念と共に「命を与える」という意味についてコリンらが気付くのである。
人間、罪を犯しても必ずやりなおせるという単純明快なメッセージをコミカルに描く、癒しと再生の物語とも言えるだろう。
可能性を摘み取らないで
本作は、ガーデニングの国イギリスならではのユーモアに満ちた佳作だと言えよう。社会から隔絶され、世間に戻る道を忘れ、出所してもまた刑務所へと戻ってくる…この負の連鎖は、いくら厳罰化を推し進めても断ち切ることは出来ない。「受刑者を信頼して外に出したら何をするか分からない」「安全な社会を確保するためにも、厳罰化しなければいけない」といった意見も良く耳にする。しかし、もし本当に社会を安全にしたいなら、再犯を減らす必要性にこそ着目すべきではないだろうか。
「更生させられる」ではなく、「更生する」ように促すという発想。長い目で見て必要なのは、人間の可能性を信じることだ。せっかくの可能性を摘み取り、花を咲かせないまま閉じ込めていたって、何も生み出さないのである。
Lenny The Kid
ブルベイカー(Brubaker)

- 公開
- 1980年、アメリカ
- 監督
- スチュアート・ローゼンバーグ
- 主演
- ロバート・レッドフォード、モーガン・フリーマン
護送車から降りて
アーカンソー州ウェイクフィールド刑務所。この州立刑務所は、囚人たちによって自治運営がされているという、極めて画期的とされる刑務所である。刑務所の敷地近くで、銃を持った数人の男たちが血塗れで瀕死の囚人を1人運んでいく。護送車に乗せて一緒に刑務所に連れ戻すのだった。脱獄しようとした囚人を、自治にあたっている囚人たちが撃ったのだ。ここでは看守の人手不足を補うために看守代行として銃も持たされた模範囚数名は、自治という美名のもとに暴力を許されている。これからこの刑務所に入ることになっている新入りたちの顔が凍りつく。
小雨が降りしきる朝早くに、新入りの囚人たちを乗せた護送車が刑務所に辿り着いた。その中に主人公ブルベイカーもいた。しかし刑務所側は誰も、撃たれて瀕死状態にある囚人を介抱しようとしない。新入りたちは護送車を降り、雨でぬかるんだ道を歩いて建物へと入っていくのだった。
異常なシステム
新入りたちは、すぐに身に沁みて気付くことになる。
看守から良い扱いを受けるために賄賂が横行し、多くの人間が押し込められている汚い雑居房ではホモセクシュアル・レイプの犠牲になる弱い囚人がいる。そして、食事には生きた蛆虫が入っている。さらに非情なことに、見せしめのために囚人たちの目の前で鞭打たれる者もいる。所内の病院では治療を急ぐ囚人を後回しにして、お金が出せる囚人が優先される。看守が残した肉も売買される。…この刑務所は悲惨な状態なのだ。誰もが異常だと感じているのに、誰も逆らえない強力なシステム。それがウェイクフィールド刑務所の真の姿だったのだ。
刑務所の所長
ある日、囚人ブルベイカーが独房の清掃をしていると、痩せて険しい顔つきをした男が独房から飛び出してきた。その男は囚人ブレンを人質にとり、「所長を呼べ!」と叫ぶ。彼は自分たちを人間として尊重されていないと訴えるのだった。そこで、ブルベイカーは自分が新任の所長で刑務所の実態を調査している最中であると話し、その男を独房に戻す。
最初、看守も囚人も、これを機転の利いた嘘だと思う。しかし、その嘘は本当だったのである。そう、ブルベイカーは所長になる前に実情を知るため、身分を隠して刑務所に潜り込んでいたのだ。
ブルベイカーは受刑囚の一人だと思って観ているので、観客は驚かされるだろう。その驚きは映画中の囚人たちの驚きと一致するもので、脚本が優れていることを実感させられる。
改革の行方…
正式に所長となったヘンリー・ブルベイカー。就任する前に自分の身をもって行った実態調査は、根本的な改革の必要性を示していた。まず彼は、日が全く当たらない真っ暗な独房に入れられていた囚人たちを日光の下に出し、投票によって囚人自治委員を組織させる。
ある日、老朽化した建物が壊れて多くの怪我人が出た。その際に、非常勤の医師が囚人から金を取って治療していること、そのために金のない囚人は満足な治療さえ受けられないでいることが分かり、ちゃんとした治療を行える医師の常駐の必要性も分かってくる。さらには、大量の殺人が行われており、刑務所の敷地内に死体を埋めることで殺人の事実を隠してきたということまで突き止めるに至るのだった…
ラストシーンでは、ブルベイカーは事態を隠蔽しようとする行政によって所長を首にされて刑務所を去ることになる。しかし囚人たちは新所長が止めるのも聞かず、車で立ち去るブルベイカーに対して敬意を込めて拍手を送る。そのシーンは、ブルベイカーの改革が囚人にとって、どれほど切望されていたかを表していると言えよう。
物語ではなく現実として
この映画は、1967~68年にかけてアーカンソー州の刑務所所長を務めた実在の人物トーマス・O・マートンが、自らの体験を書いたノン・フィクション・ベスト・セラーを映画化したものである。1980年度のアカデミー賞脚本賞にノミネートされている。このような刑務所が存在したということが、実際に現実の問題として大衆の前に突き付けられたわけである。
この映画の素晴らしい点は、その脚本が優れていることだけではなく、所長役のロバート・レッドフォードの演技であろう。あまり多くを語らないが、その鋭い目付きは真実を見つめ、正義感に満ちた所長が手探りでこの残虐なシステムと闘いながら刑務所を改革していくさまを好演している。彼以外では、この役をここまで自然にシリアスに演じきることはできなかっただろう。
隠す者と暴く者
異常なシステムであったとしても、それが続けば人々はそれを受け入れてしまう。残虐な行為であっても、感覚が麻痺していれば平気で行えるようになる。ある意味で、体制側の者たちもまた、このシステムの被害者なのだ。 そして、外部に隠し続けてさえいれば、問題にはならない。しかし、本当にそれで良いのだろうか?…答えは、Noである。蓋をしておいたって問題は解決しない。特に、人の命さえも奪っていくような体制のもとでは、日々、被害者が増えていくだけだ。
ここで我々の頭に甦ってくるのは、名古屋刑務所事件である。革手錠が使われたことで多くの受刑者が重傷を負い、命を落とした。これは当初、刑務官個人の残虐な行為に過ぎないとされていた。しかしながら、それを許し助長するシステムこそが最も問題なのだ。隠されていた真実を暴くこと、体制そのものにメスを入れ変えていくこと、その勇気を見せてくれる作品である。映画中の囚人と共に、ブルベイカーに拍手を送りたい。
グアンタナモ ~僕達が見た真実~

- 公開
- 2006年 イギリス
- 監督
- マイケル・ウィンターボトム
- 主演
- ローヘル・アフマド:ファルハド・ハールーン、シャフィク・レスル:リス・アフメッド、アシフ・イクバル:アフラン・ウスマン
結婚式を目前に控えて
アシフ・イクバルはパキスタン系イギリス人で、ごく普通の青年だった。彼は故郷パキスタンに帰って結婚を決意し、親友であるローヘル、シャフィク、ムニールを式に招待する。それは折りしも2001年10月…ニューヨークを中心に全米が9・11事件で悲しみの底にある中で、米英軍がアフガニスタン空爆に踏み切った時のことであった。
パキスタンで4人は隣国での空爆の噂を聞き、その真偽を確かめようと国境を渡ることを思い立つ。困っている人を助けてあげられるかもしれないし、何よりアフガニスタンのナン(カレーなどを付けて食べるパン)は大きくて美味しい。ちょっとした観光にもなるだろうと、彼らはアフガニスタンへ向かったのだった。
これが国境?
国境を越えるというと大それたことにも聞こえるが、何のことはない、特に誰かに止められることもなく彼らを乗せたバスはアフガニスタンに入国。あまりの呆気なさに4人は驚かされる。
しかし、次の日に実際に空爆に遭遇して彼らの認識は変わる。さらにアシフが病気になり、空爆の被害者に対して自分達が何もしてあげられないことも分かってくる。彼らは自分達の無力さを感じつつパキスタンに帰ることにするが、北部同盟がタリバンの前線を突破したために激しい爆撃に晒されることになる。九死に一生を得て爆撃の中を生き残ったアシフ、ローヘル、シャフィクだったが、米軍に拘束されシェベルガーン捕虜収容所へ送られることになってしまうのだった。
「捕虜でも犯罪者でもない敵性戦闘員」
英語が喋れること、そしてイギリス人であるということが、ここで災いする。尋問・拷問によって口を割らせて情報を聞き出すには英語が話せる者である方が好都合だし、イギリス人なのにテロに加担したとなれば裏切り者である。3人はグアンタナモ基地にある収容所へと移送されることになった。
このグアンタナモというのはキューバにある広大な米軍基地であり、約100年前からアメリカが半永久的に借用しているものである。キューバ政府は返還を求めているという。ここには捕虜でも犯罪者でもない国際テロリストとされた容疑者が約500人も収容されている。アメリカの法律も国際法も適用されず、司法手続すら受けられないまま拘束されているのである。
鉄条網の内側で
特に驚かされるのは、このグアンタナモの収容所の状態である。釈放された彼らがインタビューの際に当時を思い出して、「動物園のようだった」と語っている。これには、何の誇張もない。いや、もしかしたら動物園より酷いかもしれない。昼間に太陽が照りつける屋外…目隠しとヘッドフォンで外界から遮断されたまま、鉄条網の中で正座させられている。夜は、やっと1人が眠れる程度の狭いフェンスの中に入れられる。そこにはバケツが2つ…1つは飲み水で、もう1つはトイレ。喋ってもいけないし、フェンスに触ってもいけない。そして、アッラーへの祈りも禁止である。
物のように扱われたり、尋問という名の拷問にあったり…映画の途中に流れるインタビュー・シーンでアシフ本人が語る。「想像もつかないような状況に巻き込まれて追いつめられた時、人は潰れてしまうか強くなるかだと思う。僕は強くなった。」
秘密拘禁施設
この映画によって強く意識させられるのは、内部が秘密になっている施設の潜在的な危険性である。外部からのチェックも何もなければ、どこまでだって劣悪になりうるのだ。閉鎖性と密室性…これらこそ、拘禁施設における人権侵害を助長させる最大の要因といっても過言ではないだろう。最低限の人権保障のためにも、施設の透明化は必須なのである。
その観点からすると、日本の監獄法改正によって刑事施設視察委員会が設置されたことは希望が持てることだ。しっかりと視察委員会が機能し、人権侵害の監視が図られるようになっていってほしいものである。
基地の閉鎖を願って
2006年ベルリン国際映画祭にて銀熊賞(監督賞)を受賞した本作品は、実際にアシフらの体験をもとに作られたものである。ウィンターボトム監督は「グアンタナモ基地閉鎖を願って制作した」と語ったという。国連拷問禁止委員会もまた06年5月に閉鎖を勧告している。
この作品は、日本では1月からロードショーであるとのこと。映画館に足を運んで観ることを、お奨めしたい作品である。小難しい国際問題としてではなく、青年たちの友情そして成長の軌跡を描いた映画としても観ることができるだろう。
テロに対する戦争という口実を使って、一体、何が行われてきたのか?報復によって続く“負の連鎖”…それを断ち切るためにも、僕達が見た真実を多くの人々が見て知ってほしいと願って止まない。
Lenny The Kid